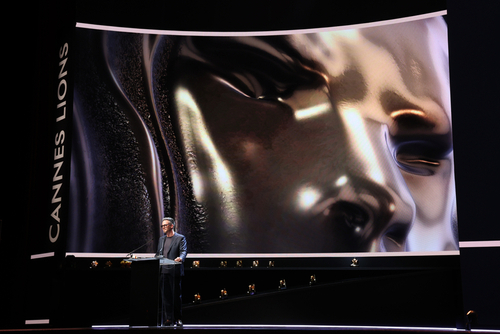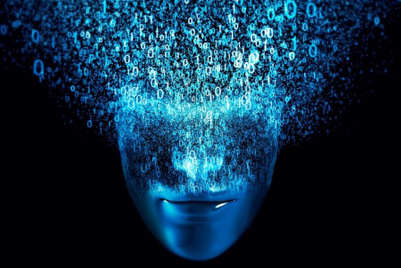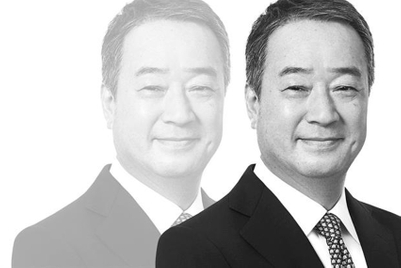.png&h=570&w=855&q=100&v=20250320&c=1)
産業革命以来、人は常に新しいテクノロジーに適応する手段を模索し、その試行錯誤が人の思考や行動に波及効果を与えてきた。
本来我々にとって、「自然な交流」とは生身の体を使った直接的なものだ。だが今では、「いいね!」や絵文字がそれに取って代わってしまった。友人付き合いとは「フォロー」をクリックすることであり、求愛はスマホを右にスワイプすることになった。こうした変化は人同士の関わりに確実に影響を与え、人間関係を表層的なものにしてしまう。
また、人は本来、有意義で充実した仕事に就きたいと考える。しかし工業化と科学に基づいたマネジメントのニーズによって、多くの人々が反復的かつ機械的な仕事を強いられている。シンガポール国立大学のジャヤンス・ナラヤナン准教授は、「経済的理由から、こうした変化が人間を単なる機械の延長に変え、燃え尽き症候群や過労を引き起こしている」と話す。
テクノロジーは飛躍的な経済的発展をもたらしたが、人の本義的な「デザイン」を変え、心身に悪影響を及ぼす。だが、大量のデータと機械学習に基づいて新たなコンテンツを創造する生成AIは、活用次第でその潮目を変えてくれるかもしれない。
2022年後半に登場したChatGPT 3.5は、人間の言葉を理解し、質問に答え、エッセイや手紙、ストーリーを作成する能力で世界を驚かせた。生成AIは以前からあったが、こうした自然言語処理によってその人気は爆発的に広まった。
調査ツール「ブルームバーグ・インテリジェンス」は、生成AIが2032年までに世界で1兆3,000億米ドル規模の市場に達し、潜在成長率は年率42%になると予測。また「プレシデンスリサーチ」によれば、最も急成長している市場はアジア太平洋地域(APAC)だという。
この技術革新が象徴するのは、テクノロジーが本来の人の姿に近付き、その逆に非ずという、人とテクノロジーの関係の変化だ。それは生成AIが人間の考え方や行動に影響を与え、文化的波及効果をもたらすかもしれない。
そして人は、人間であることの真の意味を受け入れられるようになるかもしれない。つまり、目的を持って働き、共感を抱きつつ人間関係を育むようになるのだ。
マッキンゼー社によると、アジアの人々は世界平均よりも高い割合で燃え尽き症候群に陥るという。アジアでは長時間労働や複数の仕事を持つこと、ワークライフバランスの欠如は「ハッスルカルチャー」によって美化されている。若い世代は今、こうした考え方がもたらす様々なストレスを目の当たりにし、それを避けるための模索を始めた。
その1つが、生産性を高めるテクノロジーだ。GWIの調査結果によると、オーストラリアや日本、中国、インド、シンガポールのZ世代とミレニアル世代のほぼ半数が、「AIツールの進歩が職場を改善する」と考えている。セールスフォースによる市場調査では、生成AIのユーザーの65%はこれらの年齢層だ。
生成AIは基礎的な作業から人を解放し、人はより大局的かつ重要なテーマに多くの時間を費やせるようになる。ユーアイパス社による世界規模の調査では、「AIによる自動化が燃え尽き症候群を減らし、仕事の充実感を高める」と考える労働者は60%近くに及んだ。
中国のアリババは、生成AIを職場のメッセージング・アプリ「ディントーク(DingTalk)」に統合し、会議の要約を書かせたり、パーソナライズ化されたスケジュールを作成させたりといった、通常なら何時間もかかる作業を生成AIに委ねている。
様々な仕事が数秒でこなせるようになれば、もはや労働時間によって生産性のレベルが決定することはない。創造される価値はバランスの取れたライフスタイルと融合し、「効果的労働」の象徴となる。
生成AIは仕事の本質を変えるだけでなく、「共感」を深める可能性も秘めている。米国の小説家ハーパー・リーは名著『アラバマ物語』で、「その人の視点で物事を考えなければ、その人のことを本当に理解できない 」と書いた。生成AIは、人が己のバイアスを超えて、別の視点から物事を見ることを可能にするのだ。
文化的イベントはしばしば包括的エクスペリエンスとして理解され、アプローチされるが、「瞬間の記憶」は個人的なものだろう。マイクロソフトはこの点を踏まえ、休日とは各人にとって何を意味するのか、生成AIを使ってそれを視覚化した広告を作成した。ある人にとってそれは折り紙を折ることであり、またある人にとっては友人や家族と一緒に餃子を作ること……マイクロソフトはテクノロジーを通じ、いかにオーディエンスと個人的関係を築くかを示した。
人の知覚には、その人の精神状態が加味される。したがって世界観の共有は極めて難しい。R/GAシンガポールとシンガポール精神衛生協会(SAMH)は、テキストを画像に変換する生成AIを活用し、精神的疾患を抱える人々が自己を表現する展覧会を開いた。ある統合失調症の男性は、ビルの屋上に座る巨人の画像を出展。これは、ビルの11階に住んでいても1階の住人の声が聞こえてくる日常を描いたものだ。
以前は、他者の経験や考えをイメージすることは難しかった。だが今ではテクノロジーがそれを可能にした。これによって、人同士の様々なギャップが埋まる可能性がある。
例えば、10代の若者の本当の考えを親が知ることができたり、逆に親の考えを若者が知ることができたら……。相反する2つの文化が互いの考えを視覚化し、違いよりも類似性を発見できたら素晴らしいことだろう。ブランドは生成AIを使って、消費者が他人の視点で理解することをサポートし、障壁を取り除き、より深い絆と共感を育むことができる。
生成AIは多くの可能性を秘めているが、リスクも無視できない。中でも危険なのは、ステレオタイプや実現不可能な美の基準を広めてしまうことだ。
インド、インドネシア、フィリピンなどで人気のアバターアプリ「レンザ(Lensa)」やテンセントが作った「Different Dimension Me」は、ユーザーが写真をアップロードし、AIが生成したイメージに変換することができる。一部のユーザーは自分の体型が性的に強調されたり、肌が白くなったりしたと訴えた。さらには、知的財産権(IP)の侵害も懸念されている。
生成AIは、人とテクノロジーの関係が変化していることの象徴と言える。テクノロジーが我々の話し方や思考に近付けば、我々の行動と文化に波及効果をもたらす。燃え尽き症候群や偏見といったマイナスの文化を、有意義なサービスの提供や他人を思いやる文化に変えられるかもしれないのだ。
それを実現できるか否かは、メディアが何を伝え、何をスタンダードにするかにかかっている。集団的な思考を積極的に生み出す役割を担うマーケターは、誠実さを広め、テクノロジーを活用することで、人類が本来持つ尊い目的と共感の再生を図っていかねばならない。
エリザベス・シー氏はUM APAC のシニア・リージョナル・ストラテジストを務める。