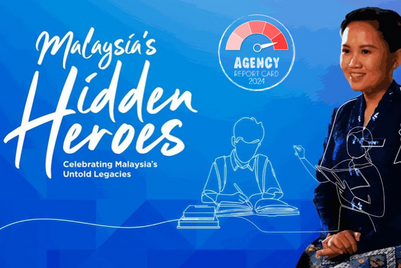.png&h=570&w=855&q=100&v=20250320&c=1)
ポストデジタルの世界において、パブリッシャーが利益を上げることが、以前よりはるかに困難になったのは周知の事実だ。グーグルとフェイスブックが全世界のデジタル広告費の80~90%を占めており、東南アジアでも、現地に強力なライバルがいるにもかかわらず、やはり広告費の大半を占めている。
同様にブランドにとっても、従来型の広告戦略の効果が低下しており、やはり厳しさが増している。現代の消費者は広告への信頼を失い、クリックベイトに引っかかることなく、あからさまなブランドプロモーションはスクロールして通り過ぎ、欺瞞的な宣伝文句は瞬時に見抜くことができる。しかも、ブランドがデジタル広告戦略を練る際には、Cookieの廃止やiOS 14のリリースに伴う広告識別子(IDFA)の影響も考慮する必要がある。これらの傾向は顧客獲得に劇的なインパクトをもたらした。とりわけ、CPMベースの広告をパブリッシャーに依存してきたブランドにとっては影響が大きい。
したがって、窮地に立たされたパブリッシャーが、ブランドにとって費用対効果と透明性の高い方法でコンテンツを収益化する方法を見つけるなら、相互にウィンウィンの関係を築くことができる。
そこで登場するのがコンテンツコマースだ。
コンテンツコマースとは?
簡単に言えば、プロダクトプレイスメントのデジタル版だ。例えば、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を観ながら、マーティ・マクフライが履いているナイキのスニーカーをクリック一つで購入できる(あるいは、映画を観た人がナイキのスニーカーを購入するとリワードが還元される)と考えればよい。コンテンツコマースを大別すると、次の3種類になる。1つ目はコンテンツに関連した商品の直接購入(eコマース)、2つ目は商品リンクのクリックスルー(アフィリエイトモデル)、3つ目は、コンテンツが商品の購入に関与した場合、購入経路における貢献度を割り当てること(アトリビューションマーケティング)だ。
これこそが先に述べたウィンウィンの関係だ。パブリッシャーは既存のコンテンツから追加の収益を得ることができ、ブランドは成果を上げたリンクに対してのみ支払えばいい。言い換えるなら、パブリッシャーはオーディエンスを売るのではなく、オーディエンスに対して売るかたちに移行することになる。パブリッシャーやブランドが、サードパーティのパートナーに管理を依頼するのではなく、直接トラッキングし、報酬を支払い、貢献度を割り当て、さらにはこれを容易に最適化できる技術が開発されたことで、コンテンツコマースは急速に普及し始めている。
パブリッシャー、ブランド、そして何より消費者にとって、コンテンツコマースには以下の4つの利点がある。
1. 本物であること
質の高いパブリッシャーは、本物であり、信頼でき、親近感があることによって、忠実なオーディエンスを獲得している。これは、編集上の整合性を維持しつつも、購入可能な商品へのリンクが読者にとっても価値を持つことを意味する。ニューヨーク・タイムズが、2016年に消費者向けガイドブックのワイヤーカッターを約3000万ドルで買収したとき、同社は当然ながらこの点を意識していた。コンテンツコマースは広告とはまったく異なるビジネスであり、パブリッシャーがどのブランドと提携するかの権限を持つため、主要な読者層に対し最適なブランドを選択することができる。
パブリッシャーは長い年月をかけて読者との信頼関係を築いてきた。ブランドは「広告主」としてではなく、「パートナー」として、パブリッシャーとともに本物のコンテンツをつくりだすことで、そうした信頼関係を活用すべきだろう。
2. コンテクスチュアルな顧客体験
在宅勤務が浸透したことで、消費者はこれまで以上にコンテンツを読み、閲覧し、消費するようになり、オンラインで注文するアイテムも増え、買い物で心を癒す機会も増えた(これはもしかしたら筆者だけかもしれないが)。しかし同時に、視聴の邪魔になるようなオンライン広告に対する許容度は低下してきている。ネットフリックスのドキュメンタリー映画「監視資本主義:デジタル社会がもたらす光と影」などをきっかけに、消費者データの利用に関する懸念も、主要メディアや日常会話で語られるようになった。コンテンツコマースは、コンテクスチュアルで中断のない、かつ有益な体験を消費者に提供することで、これらの課題の両方に対応している。
3. データのインサイト
パブリッシャーは往々にして、読者が実際に何を購入しているかを把握できない。その主な理由は、通常、パブリッシャーがCPMベースのキャンペーンにコンバージョン測定用のピクセルを設置することを、広告主が許可していないからだ。広告主との確固としたパートナーシップと適切なテクノロジープロバイダーが揃えば、パブリッシャーは広告主のウェブサイトで消費者の行動を追跡でき、購入に関するインサイトを得ることができるようになる。このようなインサイトは、パブリッシャーが購入促進に最も効果的なコンテンツを理解する助けになるだけでなく、将来の販売交渉においても、役立つ貴重なデータをもたらしてくれる。
4. アドテク税の回避
適切な技術を導入し、大規模な管理を行うことができれば、パブリッシャーは従来の広告サプライチェーンで得られる利益よりも、コンテンツコマース取引から得られる利益で利幅を増やすことができる。なぜならブランドと直接取引することで、延々と連なるアドテクの中間業者を回避することができるからだ。
それゆえ、ニューヨーク・タイムズがワイヤーカッターを買収して以降、他のパブリッシャーがこれに追随していることも意外ではない。「シカゴ・トリビューン」「ニューヨーク・デイリーニュース」といった米国の新聞社を所有するトリビューン・パブリッシングは、商品レビューサイトを運営するベストレビューズ(BestReviews)の株式の過半数を取得した。ハースト婦人画報社が発行する「ウィメンズヘルス」の日本版は、新しいダイエットプログラムの記事に、ヌーム(Noom)アプリのダウンロードリンクを掲載している。
グーグル、テマセク(Temasek)、ベイン・アンド・カンパニーは共同で発表したレポートの中で、東南アジアの主要6市場におけるeコマースは、2025年までに約1720億ドル(約18兆8000億円)規模に達すると予測している。ロックダウンの影響もあり、東南アジアではeコマースが力強い成長を遂げており、コンテンツコマースのチャンスはますます拡大している。2021年中にこのチャンスをどのパブリッシャーやブランドが手にするのか、関心を持って見守っていきたい。
サム・モートン氏はパートナーシップオートメーションテクノロジー企業インパクトのアジア太平洋地域パートナーシップディレクター。