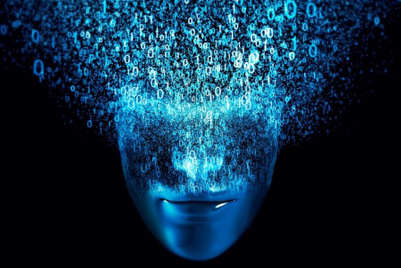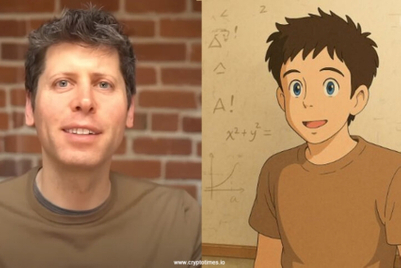FHJのグループプレジデント就任から1年を振り返って、いかがでしたか?
経営機能としてのコミュニケーションの重要性が、日本のビジネス界全体で急速に認識されてきていることを実感する一年でした。日本企業のグローバル化は勢いが加速していますし、不祥事に対する注目度は上がり、海外企業の国内企業に対する買収提案も増えましたよね。そういった中で、企業と社会、企業とステークホルダー、企業とグローバル社会の関係性を問われる瞬間が増えてきていることを、多くの方々が痛切に感じ始めているように思います。
日本市場は、日本語を中心とした文化が揺るぎない形で今まで受け継がれ、メディアやPRの世界もそれによって形作られてきました。また日本の多くの企業には、できるだけ自分たちで対応していくという自前主義が根強く残っています。その一方で、グローバル化やデジタル化が進み、自分たちのロジックだけでは通用しない世界が急速に広がってきています。
従来型のモデルと新しいモデル、あるいは日本語を中心とした世界と英語中心の世界、その両方にしっかり目配りしていかないと、クライアントのニーズを満たすことができない。PRを本業とするプロフェッショナルにとって、甘くない市場だと思います。
企業で広報を担当してきた経験は、どのように活きていると感じますか?
FHJで経験を積んだ後、企業側で広報やコミュニケーション、マーケティング、ブランディングに17年間携わる中で、社内の意識改革やブランドイメージなど経営戦略を実現していくための広報活動や、クライシス対応も経験しました。経営機能としてのコミュニケーションをいかに研ぎ澄ましていくか、そしてその機能を使い切れる体制をいかに組織の中にビルトインしていくかに力点を置いて、経験を積み上げてきました。経営者視点で必要なコミュニケーションを、個別の機能の垣根を越えて発想し、提案し得ることが強みだと思います。
トップマネジメントの視点で行う広報は、横串機能です。平常通りに物事が進んでいる間は、顧客には営業部が、従業員には人事部が、株主や投資家には財務部が、それぞれ縦割り構造でコミュニケーションをとっていても、大抵のことは滞りなく流れます。しかし事故や事件、不祥事といった予期せぬクライシス、あるいは現状を打破するために意図的に変革を仕掛ける際には、コミュニケーションがちぐはぐだと大きな混乱を招きかねません。
これをグローバルで対応するとなると、事態はより一層複雑になります。ステークホルダー、拠点、言語、文化などが広範囲にわたる場合には、横串を通して一糸乱れずに伝えていくコミュニケーションを、経営の視点に立ってデザインしていく必要があるのです。
日本法人で今年3月に「グローバル有事対応デスク」というサービスを立ち上げた背景を教えてください。
日本企業のグローバル化が加速し、生産拠点も売上も海外が半分以上を占めるような企業が増える一方で、コーポレート・アフェアーズ機能のグローバル対応が十分に整っていないというケースは少なくありません。中でもコミュニケーションは、その土地ならではのローカル色が強い領域です。日本では考えもしないような関心事が現地にはあり、日本語で書いたものをそのまま翻訳しても全く伝わらなかったり、誤解が生じてトラブルにも発展しかねない。コミュニケーションのチャネルや、伝える内容も多様化してきています。起こり得るリスクをいかに抑えていくか、あるいはきちんと伝えることでマーケティングに活かしていくか。守りと攻めの両面を、複数の拠点や地域、多様な文化、さまざまなステークホルダーに展開していくのは、かなり難易度が高いことです。
そういった潜在的なニーズへの対応の一つとして「グローバル有事対応デスク」を立ち上げました。予期せぬ形で有事が起きた際にどうすればいいのか、発生してから考え始めたのでは遅いのではないかと心配される声を、さまざまなところで聞きます。そこで、こういうパッケージにして打ち出した方が、お声かけいただきやすくなるのではと考えました。
外資系のPRファームというと、外資系企業を相手に事業をしているようなイメージを持たれがちですが、グローバル化はもはや外資系企業や一部の大企業だけの話ではなくなってきています。当社は堅牢かつ機動的なグローバルネットワークが最大の強みなので、グローバルと無関係でいられなくなった今こそ、日本企業のお役に立つべきという思いです。
昨年から日本法人では「元気塾」という勉強会を社内で開催し、社会のさまざまな課題をテーマに有識者を招いていますね。
先ほど、広報は横串機能だと言いましたが、これは日本社会の縮図だとも思います。専門領域や業界、地域などさまざまなところで縦割りになっているものに、横に串を通すようなコミュニケーションをしていくリーダーが増えていけば、企業は活性化し、社会全体も、そこに住む人々や働く人々も元気になっていけるのではないか。そういうお手伝いをするのが、私たちの仕事だと考えています。
そのため、社会ではどのようなことが今テーマになっているのか、人々は何に困り、何に関心を持っているのか。こういうことを提案し得る立場にある私たちは、日頃から研鑽を積み、アンテナを人一倍高く持つことがとても重要です。当社は「コミュニケーションのパワーで日本をもっと元気に」と掲げていますが、そのためにはまず自分たち知的に元気でありたい。そうすることでクライアントの課題に対しても、ユニークな解決策を提案できるのではと思います。
今後、どのような領域に注力していきたいと考えていますか?
フライシュマン・ヒラード全体で力を入れていきたいのは「コーポレート・アフェアーズ」と「ブランド・インパクト」です。
まず、コーポレート・アフェアーズとは、企業の事業をステークホルダーから認めてもらい、操業のための許可(License to Operate)、つまり事業をサポートしてもらえるような環境を整えることです。社会や規制当局など、さまざまステークホルダーとの関係を良好に保たなくては、事業を成長拡大させることは難しいためです。
コーポレート・アフェアーズには危機管理やチェンジ・マネジメント(企業の変革を推進するための環境整備)、財務情報を伝えるファイナンシャル・コミュニケーション、パブリック・アフェアーズ(政府や世論に対しする働きかけ)、レスポンシブル・ビジネス(責任ある事業活動)などが含まれます。経営の課題をコミュニケーションの力で支援していくもので、これを強化していきます。
もう一つのブランド・インパクトは、データの力を駆使してクライアントの顧客エンゲージメントを強化し、売上拡大に直結させるという、従来の商品PRの枠組を超えていくものです。
この二つの領域とグローバルネットワークを掛け合わせて、日本発のグローバル企業の成長や市場拡大、レピュテーションの維持や向上をサポートしていきたい。そして経営に直接インパクトを与えるコミュニケーション・コンサルティングを展開していけたらと考えています。
(文:田崎亮子)