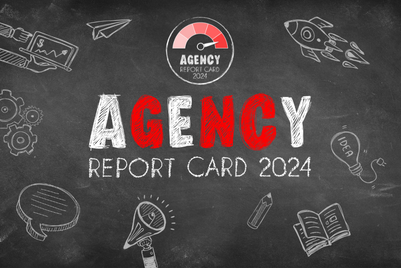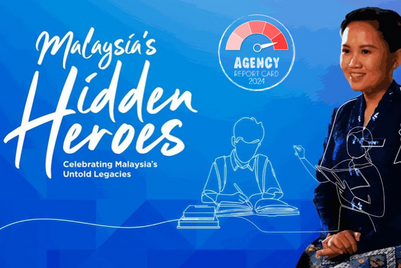* 自動翻訳した記事に、編集を加えています。
H.G.ウェルズ(英作家)の有名な言葉に「適応するか、滅びるか。それは今も昔も変わらない、避けがたい自然の命令である」がある。これは今日の博報堂にも当てはまる。129年の歴史を持つ広告大手である同社は、技術によるディスラプション、消費者行動の変化、そして熾烈な競争によって根本から変わった世界の状況を乗り越えようとしている。
博報堂が引き継いできた伝統は最大の強みであり、最大の課題でもある。消費者を複雑かつ多面的な個人としてとらえる生活者起点の発想は、長きにわたり同社の競争力となり、日本市場を非常に高い解像度で理解する上で役立ってきた。しかし伝統だけでは関連性を保証できなくなった今、広告会社はイノベーションや多様性、そして前例のないスピードでのROI(投資利益率)向上を実現しなくてはならない。博報堂にとって、これ以上の課題はないだろう。
2024年6月には、事業構造の変革に向けた3年間のロードマップとして中期経営計画を発表した。掲げる三つのテーマのうち一つが、従来の広告事業への依存度を下げ、コンサルティングやデジタルといった成長領域で5割程度の利益を生み出すというものだ。デジタルトランスフォーメーションの一環として、博報堂テクノロジーズの設立や、次世代型モデル「AaaS(Advertising as a Service)」の提唱などに取り組む。一方、最高商務責任者(CCO)モデルを新たに導入し、日本人以外の人材に経営幹部登用への道筋を初めて示した。多様化に向けた重要な一歩を、ようやく踏み出した形だ。
だが、これだけの進歩を遂げてはいるものの、その多くは競争の後追いのようにも感じられる。
このような変化は、十分な速さで起きているのか。そしてそれは同社のコアとなる部分を変革しているのか、あるいは単にうわべだけのものなのだろうか?
この計画に、リスクが無いわけではない。事業の多角化を実行するには、6つの事業領域間でのサイロ化を回避することから、一貫した顧客体験の提供まで、さまざまな課題が伴う。さらに、新規の事業領域の拡大に大きく依存する大胆な目標設定は、変化の激しい市場では見通しが不確実だ。
博報堂は大胆な変革に挑もうとしており、それは尊重すべき姿勢だ。構造変革のさまざまな課題を切り抜け、成長エンジンを始動させ、イノベーションを継続させる一連のプロセスを維持することができれば、2031年までに存在感を世界に示すことができるだろう。もしも実現したら、の話ではあるが。
今のところ、計画は野心的で、設定した目標は測定可能であり、無視できない課題もある。迅速かつ有意義な形で成果を出さなければならないというプレッシャーは、かつてないほど高まっている
| 評価方法についてはこちらから |
強み(STRENGTHS)
経済の混乱や組織統合、業界全体での人員削減が続いた1年であったが、博報堂は堅調に推移した。第3四半期の利益は厳しかったが、売上総利益は前年同期比+4.3%と明るい兆しが見える。大規模な人員整理を回避できたことも特筆すべきだ。香港オフィスの閉鎖に伴って60人の雇用が失われたが、全体として人員配置は安定していた。従業員の離職率は5.3%(2023年)から4%(2024年)に低下し、ワーク・ライフ・バランス関連の取り組みによってエンゲージメントも向上するなど、従業員の満足度と忠誠心の向上を示している。これは多くの広告会社が切望することだろう。
クライアントについては、主要アカウントをすべて維持し、3,000社を超える強力な顧客ベースを持つという。新規獲得したクライアントについて同社は詳細を伏せたが、Z世代のライフスタイルブランドや、H+(エイチプラス)が獲得したネットフリックスの地域契約などが含まれる。国外ではASEAN、台湾、米国で、収益性や成長目標が期待以上の成果を上げた。
同社は常にイノベーションに力を入れてきており、これを手薄だと非難する人はほとんどいないだろう。博報堂DYグループは、設備投資やM&Aなどに「数百億円規模の投資」を想定している。生活者のインサイト、ブランドのデータ、AI技術を融合させたプラットフォーム「H+ Intelligence」は、広告、オウンドメディア、コマース、CRMの領域においてビジネス成長を促進する。社内では「CREATIVE BLOOM PLANNING」が、戦略や企画の効率化と高度化を進めた。また、生活者を深く理解するためのサービス「バーチャル生活者」は既に10社のクライアントが取り入れている。だがその長期的な影響については、ROIやエンゲージメントなど具体的な成果に基づいて評価していく必要がある。
アマゾンジャパンとの提携も、eコマースにおける競争優位性をもたらしている。アマゾンと同社のデータを相互分析することで、プライバシーを担保しながら、アマゾンの売上に対するマーケティング施策の影響を包括的に把握できる。つまり、売上を促進する要因を特定し、広告予算を最適化し、ターゲットを絞った出稿計画を立案し、ROIのシミュレーションを行えるのだ。
同社は、アイデアに事欠くことがない。複数の取り組みを同時に管理する能力も強みで、大きな可能性を秘めた領域だ。
クリエイティブ面でも同社は素晴らしい成果を上げており、人々の共感を呼び、実際の業績につながる作品を一貫して生み出している。TBWA HAKUHODOが手掛けた日本マクドナルドの「スマイルあげない(No Smiles)」キャンペーンでは、“笑わないアーティスト”であるanoを起用。この作品は人々の心をつかみ、再生回数3,600万回以上を記録、ブランド愛着度も30%上昇し、ロンドン・インターナショナル・アワードやカンヌライオンズなどで数々の賞を獲得した。また、自分らしく働くということについて、全国的に議論を巻き起こした。
博報堂が手掛けた日産自動車の作品も、革新的なファンエンゲージメントの好例となった。2024年3月に開催された日本初上陸のEVレース「フォーミュラE Tokyo E-Prix」に日産が参加したのに合わせ、市場におけるフォーミュラEの認知度を高め、日産と生活者のつながりを強化するプロジェクトを始動。サポーターの声援を電力に変換してチームに届けた。

この取り組みは広く称賛され、141,000人以上が参加し、1,200件以上のニュースで取り上げられ、観戦チケットはわずか3分で完売。ウェブとアプリの新規ユーザー登録者数は1,200万人に達した。また革新的なアプローチが評価され、クリオ・スポーツ・アワードの金賞を獲得した。
リーダーシップについては、2024年にはクリエイティブ部門の強化のため、チャンドゥ・ラジャプレヤー氏がベトナムのECDに就任した他、ケンタッキーフライドチキンのキャンペーン「Uncle KFC」を共同制作したパティダー・アカラジンダノン氏(Wolf Bkk、タイ)、ヴィモハ・バグラ氏(ECD、インド)などが入り、市場の成長を推し進めた。
一方、出光淑子氏が博報堂DYメディアパートナーズ初の女性の執行役員に就任し、女性参画の障壁を打ち破った。シュヴェタ・シャルマ氏は博報堂データラボ・インドの責任者に就任。先端研究機関「Human-Centered AI Institute(HCAI)」の代表兼最高AI責任者には森正弥氏を迎えた。
人材、イノベーション、大胆な創造性に投資するという同社の方針は、今年度の同社を際立たせることとなった。
弱み(WEAKNESSES)
博報堂の最大の弱点は、ジェンダーの多様性において苦戦が続いていることだ。進歩はみられたものの、数字は依然として厳しい現実を映し出している。従業員に占める女性の割合はグローバル全体では43%だが、国内ではわずか28%。さらに、女性の上級管理職の割合はグローバルでは25%なのに対し、国内はわずか6%であることも憂慮すべき状況だ。部門長レベルではその差がさらに広がり、グローバルは49.7%、国内は9.7%だ。障害のある従業員は1万人以上のうち2.5%を占める。
これは新しい課題でも、博報堂に限られたものでもない。日本の文化的な規範や伝統的な性別役割意識が、女性リーダーの登用を阻む根深い障壁となっている。だが国内中心というイメージから脱却し、グローバルかつ先進的なイノベーターとしての地位確立に挑む同社にとって、国内と海外で男女比にこれだけの格差があるのは数の問題ではなく、ブランドの問題といえる。
最近ではフレキシブルな働き方、男性の育児休業、2024年の採用者の50%以上を女性にするなど前向きな取り組みもみられるが、長い道のりの小さな一歩に過ぎない。男女間の賃金格差について同社は明らかにしていないが、格差は存在していないと主張している。
多様性以外にも、収益の84%が国内事業に依存しているのは明らかに脆弱だ。ASEAN、台湾、米国などの市場で成長を遂げてきた同社だが、成長の可能性がますます限られつつある国内市場への依存度が高いことは、もはや無視できないリスクだろう。
組織体制の面では、4月1日に博報堂DYメディアパートナーズと統合し、従業員数は4,601人以上となった。統合によるプランニングとメディア対応機能の集約は、機会でもありリスクでもある。組織再編はワークフローの混乱を招くことが多いため、勢いを維持するには切り替えをシームレスに行うことが重要だ。
機会(OPPORTUNITIES)
中期経営計画(2024~2027年)には、博報堂が目指す将来像が明確に示されている。統合マーケティング(デジタルマーケティング、コマースビジネス)、コンサルティング、テクノロジー、コンテンツ、インキュベーション、グローバルの6つの事業領域を設定し、成長目標を+10%以上(営業利益 年平均成長率)+5%以上(売上総利益 年平均成長率)、+13%以上(オペレーティング・マージン)としている。
その中心にあるのは、コンサルティングへの積極的な取り組みで、アクセンチュアなど大手と競合することになる。生活者発想や価値創出の能力が、データ重視の画一的なアプローチに対抗する差別化要因になり得るというのが同社経営陣の考えだ。コンサルティング、テクノロジー、グローバルビジネスといった成長領域で、2031年度までに5割程度の利益を生み出すことを目指している。
確かにこれは大胆な賭けだ。
同社はこの計画に沿って、メディア、コマース、CRMなどのデータ、ツール、プロセスをAIを活用して統合するプラットフォーム「CREATIVITY ENGINE BLOOM」などに多額の投資を行った。このプラットフォームから得られるインサイトが、顧客獲得において重要な要素となった。中長期的にはこれをクライアント向けのサービスとして提供し、新たなビジネスチャンスを高い精度で特定できるよう展開していくことも見据えている。
インドなど新興市場や、ASEANおよび台湾での継続的な成功により、成長のための環境は整った。
一方で4月にはH+が、ネットフリックスの東南アジアと台湾のメディアAOR(指名代理店)に選ばれた。初期のROIは期待を下回ったようだが、評判の向上や、それによって一流の人材をグローバル、ローカル共に引き付けられるようになることから、この投資は正当だと経営陣は考えている。そしてこれらは、博報堂が日本を主戦場とする企業から脱却し、フルファネルに対応できるグローバルエージェンシーへと進化する上で不可欠だという。
長期的には、地域ごとにCOOを置く事業モデルが、意思決定を本社から分離し、地域のリーダーに権限を与えることにもつながるだろう。グローバル展開を見据える同社にとって、日本人以外の才能ある人材を経営幹部に登用する道筋を明確に示すことは重要だ。
同社は学習機会や研修、労働時間の削減、配偶者要件の範囲拡大、2030年度に向けたサステナビリティー関連の目標など、職場改革をいくつも推進してきた。従業員の福利厚生全般にさらに力を入れていくことで、雇用主である同社のイメージが上がり、優秀な人材を獲得するための競争にも勝つことができるだろう。
脅威(THREATS)
香港オフィス閉鎖の決定は、収益性を重視するという現実的な判断であることを示唆するものだが、戦略的には高くつく可能性がある。この地域のクライアントは引き続きリモートでサポートしていくというが、グレーターベイエリア(粤港澳大湾区)でのプレゼンス強化に注力する競合他社に、市場を奪われるリスクがある。
博報堂の社運は依然として、本国と密接に結びついており、日本の経済は厳しい状況だ。同社の海外事業の収益はわずか16%。37年半ぶりの円安・ドル高水準更新は痛手で、対処が必要だろう。
|
日産自動車
上海博報堂 データドリブンマーケティング 楊蘇瑞氏 B+: 2024年は博報堂にとって、変革と前進の年となった。新中期経営計画の初年度にあたり、今後3年の目標を達成するため国内外で事業構造の変革を実施。多様性をより反映したリーダーシップ体制への再編、次世代の女性管理職を育成する研修プログラムの新設などに取り組んだ。目覚ましく進歩したテクノロジー主導のソリューションを社内外で適用し、マーケティングサービスの拡大と、収益の大幅な成長に寄与した。クリエイティブは世界的に高く評価され、権威ある国際広告賞で多数のグランプリを受賞し、TBWA HAKUHODOはロンドン・インターナショナル・アワード2024においてアジアの「リージョナル・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー」を獲得した。最後に、博報堂は持続可能な地球環境にさらに貢献できるよう、サステナビリティーの取り組みに確固たる姿勢で臨み、数多くの気候変動対策や社会貢献活動を実施している。 |