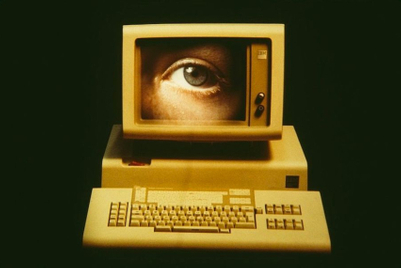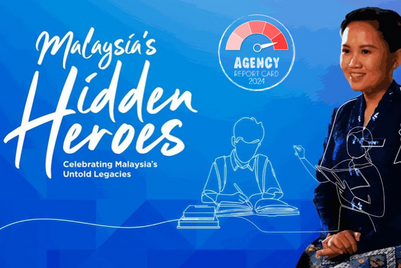増加するマーケティング部門のIT投資
「社内外のデータを統合して、チャネル横断で活用したい」「施策の効果を可視化・検証して、高速に改善を回したい」「一人ひとりに打ち手を出し分けて、異なる体験を提供したい」……。現在、マーケティング領域におけるテクノロジー活用ニーズはかつてないほどに高まり、CMOやマーケターは、自社のチャネルや業務プロセスを高度に情報武装する必要に迫られている。
背景にはデジタル化の進展がもたらす、生活者行動やニーズ、顧客接点の多様化がある。複雑化していく顧客を捕捉し続けていくには、属人/感覚的なマーケティング業務では対応が困難である。テクノロジーを活用し、得られるデータに基づき、科学的なPDCAを回すマーケティングを実現していかなければならない。
その際、近年よく見られるのは、マーケティング部門がIT部門を介さず、直接外部にアプリケーションやツールの発注を行い、独自にマーケティングシステム・プラットフォームを構築しようとする試みである。例えば、チャネルに対するMA(マーケティングオートメーション)やSFA(セールスフォースオートメーション)などのツール導入、データモニタリングシステムの整備、全体を支えるプライベートDMP環境の構築などが事例として挙げられる。これらはもはやシステム開発とも呼べる領域であるにも関わらず、マーケティング部門が予算を持って独自に執行することは、いまや珍しいことではなくなってきた。
マーケティング部門とIT部門に横たわる「断層」
このような事例の増加は、マーケティング部門とIT部門における、両者の目的意識や価値観の違いに起因するところが大きい。高い成果目標を担い、多くの施策活動を展開し、必然的にスピードとコストを重視するマーケティング部門と、基幹業務のIT化を支え、何よりも持続的な安定稼働を重視してきたIT部門の間には、潜在的に深い溝があった。つまり、従来からマーケティング部門は、すぐに使えるものを用意できないIT部門に、IT部門は、定まった要求を示しきれないマーケティング部門に、それぞれ不満を抱えていたとも言えるだろう。ここに、クラウドを前提としたソリューション・技術の進化が新たな選択肢を生んだことで、システム開発はIT部門のみの聖域とは呼べなくなってきた。
企業のデジタルシフトはまだ始まったばかりであり、マーケターはテクノロジーの活用なくしては実現困難な、高精細・高効率・高速な業務をますます要求されていく。従って、このようにマーケティング部門がITのオーナーシップを拡大していくことは不可逆の流れと考えられる。
マーケティングシステムを担うために
しかしながら、独自にプロジェクトを進めた結果、失敗したり混乱が生じているという声を耳にすることもまた多くなっており、場合により大きなリスクとなり得ることを認識すべきである。
果実を得るためには、同時に責任が生じる。以下のような、IT部門がこれまで背負ってきた重い役割を、必ずしも専門家ではない組織がどう担うかをよく吟味しなければならない。

上記はごく一例であるが、いずれも従来のマーケティング部門のままでは果たすことが難しい責任である。つまり、デジタル時代における必然の方法論のように語られることもある「IT部門外し」は、実際には茨の道ともなり得るのだ。デジタル化のスピードに対応するため、走り出すことも重要ではあるが、一方でマーケティング部門に求められることは、仕組み化に関わる自身の果たすべき役割を明確に認識することにあるだろう。そしてその実現には、これまでシステムを担ってきたIT部門との連携・協業の観点が欠かせない。特に近年増加している「デジタルマーケティング」を冠する組織には、このような取り組みが大きく期待される。
また、このような組織の自己変革は、マーケティング部門だけでなく、IT部門にも同様に求められる。事例の増加が意味するところを捉え、マーケティングとITの間に横たわる断層をどのようにして越えるか、それぞれの立場からの取り組みが必要である。
高田晴彦
電通デジタル
デジタルトランスフォーメーション部門 顧客エンゲージメントデザイン事業部
部長/コンサルティングディレクター
(編集:田崎亮子)