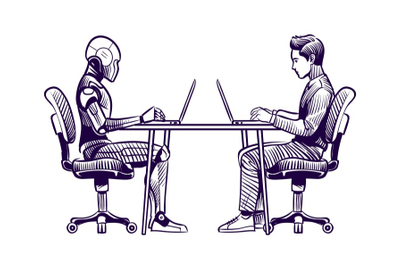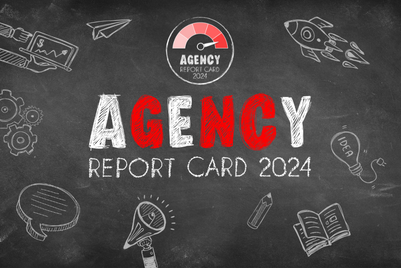この年次調査は、世界54カ国のメディア及びエンターテインメント部門での消費者支出や広告収入などの予測数値を弾き出す大規模なもの。今年のリポートでは、日本に関してメディア部門の急成長を指摘している。以下、その要点を抜粋。伸び率は年平均成長率(CAGR)を表す。
オンライン広告は、もはや「成長の牽引車」ではない。
日本のオンライン広告収入の伸び率は2021年まで5%弱で、約143億米ドル(約1兆5700億円)に達すると予測。日本は世界有数の市場ながら、最大の米国市場の規模は圧倒的。成長率は約10%で、1162億ドルになる。米国のオンライン広告収入は既に725億ドルで、テレビ広告収入の706億ドルを上回っている。日本でも両者の差は埋まりつつあり、2020年から2021年にかけてテレビ広告は159億ドルに落ち込むという予想だ。
モバイル成長の推進役となるのは、アプリ広告。
日本のモバイル広告市場は既に35億ドル規模で、2021年までには55億ドルに。成長のカギはプログラマティックバイイングだが、アプリ紹介サービスのタップジョイ(Tapjoy)社と昨年契約したLINEのようなプラットフォームも、モバイルアプリ広告の需要増加で恩恵を浴すだろう。
オンライン動画は、依然強力。
今後5年間で動画広告収入は他のディスプレイ広告を徐々に引き離し、2021年までに7.5%の成長を遂げ、4億4600万ドルになる。他のディスプレイ広告は横ばいなのに対し、動画やモバイルの伸びは堅調。ユーチューブやアンルーリー(Unruly)社などにとっては楽観的材料で、米国のモバイル動画市場は162億ドルに達する。また、ブランドが発信するオンライン動画の成長性にも注目。テレビ広告は視聴者のライフスタイルの変化やCMスキップ機能などで、妥当性を失っていくという。
オンラインテレビ広告は、この5年で10億ドル市場に。
従来型の放送局は有料のオンラインサービスに注力してきたが、広告収入を基盤とした無料サービスが急速に成長する。Abema TV(アベマティーヴィー)のようなプラットフォームがオンラインテレビ広告市場を活性化させ、米国に次ぐ世界第2位の規模になる。
2021年になっても、ホームビデオはインターネット映像配信よりも強い。
それでもネットフリックス(Netflix)のような企業は、大きな可能性を秘めている。インターネット映像配信市場は14.5%の成長を遂げ、5年以内に20億ドル規模に。ネットフリックスもアマゾンも、引き続き国内向けコンテンツに注力していく。ただし、ソフトバンクと業務提携して同社のスマートフォンにアプリがプリインストールされているネットフリックスに、一日の長がある。
プログラマティックトレーディングにどれだけ理解が広がるかは、疑問。
日本のメディアが、プライベートマーケットプレイス(PMP)の構築にどれだけ成功するか次第だろう。PMPはパブリッシャーが広告主のタイプや掲載する広告に関してより発言権を持つ、限定された広告取引市場。プログラマティックはもちろん、検索や自動化されたアドネットワークも含め、成果主義に基づく広告への需要は確実に高まっている。
早々とeスポーツのスポンサーになるのは効果的。
米国や韓国などではeスポーツ市場は巨大だが、日本はまだ始まったばかり。現在の市場規模は500万ドル弱で、2021年までには36%の伸びを示し、2300万ドルになる。「リーグ・オブ・レジェンド」のような世界的人気を誇るゲームで強力な日本チームが編成されたことや、ニンテンドースイッチが国内トーナメントを活性化していく可能性などについても注目。この分野のスポンサーシップはまだ多くはないが、通常のスポーツのスポンサーシップよりもハードルが低く、成長を期待できる。適切なビジョンを持ってサポートしていくことは、ブランドにとって十分意義があるだろう。
VRへの支出は、ブランドにとってまやかしではない。
今では誰もが仮想現実(VR)に夢中、と考えがちだ。実際この分野は著しい成長を遂げる。今年5億ドルだった市場は、2021年までに20億ドルに。VRビデオがVRゲームを凌ぐ今年、消費者向けのVRコンテンツの比重が増える一方で、コミュニケーションやユーティリティアプリへの支出は5年後も1800万ドル強にとどまる。これは、消費者市場が50億ドルであるのに対し、アプリへの支出が6400万ドルという米国の動向と比例する。
(文:デイビッド・ブレッケン 翻訳・編集:水野龍哉)













.jpeg&h=268&w=401&q=100&v=20250320&c=1)