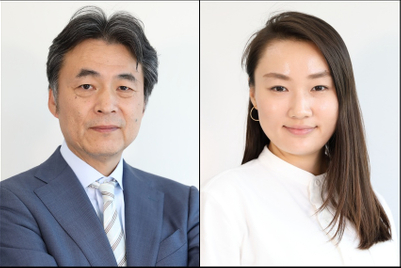マーケティング業界の指導的立場にある女性を取り上げるシリーズ、「女性リーダーたちと語る」。第2回は、オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパンのコンテントディレクターであり、オグルヴィ・パブリック・リレーションズ・ワールドワイド・ジャパンのマネージングディレクターを務める関満亜美(あび)氏に話を聞く。関満氏はロイター通信の日本支局長を経て、2015年オグルヴィに入社。このような転身は広告業界では珍しいが、優れたストーリーを語るのが広告の仕事とすれば合点がいくだろう。その一方で、ニュース報道とブランド向けのコンテンツ制作には大きな違いがあることも明らかだ。インタビューは2部構成で、前編では同氏のジャーナリストとしての経験と、それが商業的な広告の世界でどのように生かされているかを語ってもらう。後編では、「広告会社で働く日本の女性」をテーマに取り上げる。
なぜジャーナリストを志したのですか?
高校2年生になる頃には、アメリカへ留学してジャーナリズムを学ぼうと既に決めていました。英語で書く能力を身につけたかったので、それを達成するにはジャーナリストを目指すのが良いと思ったのです。
編集長として、最初に経験したことは何ですか?
ロイター東京支局のエネルギーと商品先物を担当するチームを任されました。かなりニッチな世界で、情報源はほとんどトレーダーでした。原油や金、プラチナなど様々な分野のトレーダーから情報をもらうのです。それぞれの業界やマーケットの報道のあり方を知る上で、とても良い経験でした。
原油の先物取引について面白い記事を書くのはなかなか大変ですが、もちろん最善を尽くしました。一番気に入っていたのは、北海道の大豆の先物に関するストーリー。大豆の記事を毎日書くんですが、楽しかったですよ。後に東京電力の仕事をしたときには、エネルギー市場を担当した経験が生きました。何がいつどこで役に立つか、分からないものですね。
当時、ロイターには女性のリーダーがたくさんいたのですか?
私の前任者も女性でした。エネルギー分野は、いわば「女性の縄張り」でしたね。別に、エネルギーと生理用品が似ているというわけではありませんよ。この分野は狭くニッチな世界で、トレーダーのほとんどはやり手の男性です。彼らに毎日電話をして、売りか買いかを聞き出すのです。ですから、女性相手の方がトレーダーもたくさん話をしてくれるというわけです。
当時は私が日本の編集長で、アジア地域の編集長は英国人の金髪女性でした。彼女がOPEC(石油輸出国機構)の会合に姿を現すと、誰もが「やあ、ジェニー!」と声をかけたものです。ちょっと面白い光景でした。今では考えにくいですが、1990年代ではまだ女性が珍しかったですから。
管理職としてのスタイルは、どのように培ったのですか?
これは、「日本人らしさ」という話が関わってくることですね。私に対する米国人の評価は「コンセンサス重視」で、日本人の評価は逆に「強引」。日本人の同僚は「やや親分風を吹かせる」と言い、米国人は「皆の意見に耳を傾け、考え方がオープン。合意形成を大切にする」と言うでしょう。誰の目線で見るかによって、変わってくるのです。ロイターでは外国人の上司ばかりだったので、まったく問題は起きませんでした。
ロイターの上層部は、日本人は詰めが甘いと考えていました。ですから常に、日本人に対して厳しく臨む管理職を求めていました。私は日米両方の文化を心得ていたので、それが強みとなりました。
ロイターはなぜ、日本人は甘いと考えていたのでしょう?
実際に、甘いですから。私は報道の世界やソフトウェア業界で外国人上司のもとで仕事をしました。東日本大震災後に東京電力の改革のため招聘された海外の専門家とも仕事をし、現在の広告業界に移ってからも上司は外国人です。彼らは一様に日本の企業文化と「日本は特別」という考え方に不満を持っています。
「日本ではこういうやり方をします。違うやり方ではうまく行きませんので……」という常套句に、欧米人は舌打ちするほどうんざりしています。彼らをイライラさせる科白なんですね。
例えば編集長が記者に、「今までと違うスタイルか、あるいは新しい視点で記事を書いてくれないか」と言うと、いつも決まって「いえいえ、もう日本では周知の事実ですからニュース性がありません」という答えが返ってくる。ですから編集長は、「我々の読者は日本人ではないのだから、とにかく書いてみてくれ」と言わねばなりません。
あるいは、エネルギー政策について知りたいことがあって、編集長が「厚生労働省に直接問い合わせて、XやY、Zのことを聞いてみよう」と提案したとします。記者は、「いえいえ、それは絶対無理です。きちんとした手続きを踏まなければ」と押し戻すのです。
以前に失敗しているからうまく行く見込みがない、あるいはやってはいけない決まりだから、やり方は変えられないから……こうした理由を盾に、結局何もしない人が多いのです。
仕事ではなぜ柔軟性が大切なのでしょう?
「できない」と言い続ければ、行動力がなく怠慢だと見なされます。欧米の経営陣が求めているのは、少なくとも今までとは違うことに挑戦してみようという気概がある日本人管理職です。彼らはシンプルに、「やってみましょう」という答えが聞きたいのです。
実際、これこそが欧米の企業で活躍したいと思っている日本の皆さんへの私からのアドバイスです。「うーん、それはかなり難しいですね」と言うのはやめるべきです。それだけで、あなたは「スーパースター」になれるでしょう。私の経験からしても、まずはそれだけで良いのです。
報道機関と広告会社では、コンテンツの扱い方にどのような違いがありますか?
ロイターでは、ニュースの必要性を分かってもらうために誰かを説得するようなことは一切ありませんでした。オグルヴィに移ってからは、コンテンツの必要性を理解してもらうことから仕事が始まります。
ジャーナリストやメディア企業のニュース編集室の責任者は、売り込みをする必要がありません。ニュースとは、電気や水道、ガス、空気などのように有用なものです。ロイターのような企業に勤めている人々は皆、ニュースは必要不可欠なものだと考えています。売るという行為を超越して、誰かがやらねばならないから我々がやるのだという使命感で動いています。ですから売り方を学ぶことはありません。
報道の世界では、ニュースが売れなければそれを読まない方が悪いのであって、無知ゆえの誤った選択をして生きていくならばそれで結構、といった価値観があります。一方の広告業界は、デイヴィッド・オグルヴィが残した有名な言葉が多くを物語っています。「我々は売る。そうでなければ存在する価値がない」と。
現在の仕事では、ある企業のブランドを広く浸透させる意義と、そのためのコンテンツの必要性をいかに納得してもらうか、真剣に考えなければなりません。更に広告主が対価を払うことに十分納得するよう、仕向けなければならないのです。
(文:バリー・ラスティグ 翻訳:鎌田文子 編集:水野龍哉)
このインタビューは英語で行われた。バリー・ラスティグは、東京を拠点とするビジネス・クリエイティブ戦略コンサルティング会社「コーモラント・グループ」のマネージング・パートナー。