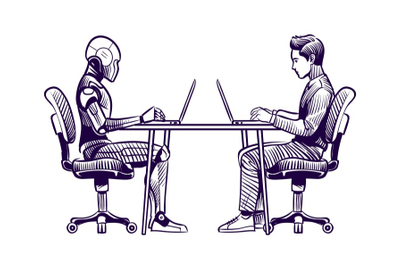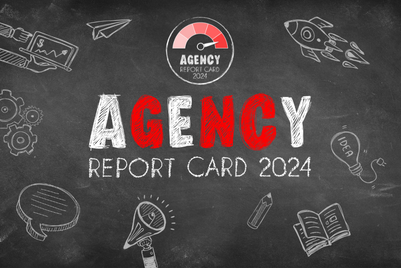| PARTNER CONTENT |
鈴木氏は2007年電通に入社し、クリエイティブディレクターとして数多くのマーケティングを主導した。その間、カンヌライオンズを初めとする国際的な広告賞を170余り獲得、2018年にはCampaign Asia-Pacificが選ぶ「40 under 40(アジアで注目すべき40歳以下の40人)」の一人に選出。今年、TikTok Adsに入社し、TikTok Ads X Design Center を立ち上げた。
昨今のトレンドであるUGCは、ブランドにとってクオリティーをどのように維持するかが喫緊の課題となりつつある。鈴木氏は、クオリティーには2つの考え方があるという。「まずは、広告業界で言うところの『クラフト』。映像などがどれだけ作り込まれているか、という視点からの定義です。もう一つは、その作品が広告的にどれだけ機能するかという視点」。
そして今のデジタルネイティブ世代(1990年代半ば〜2010年生まれ)の特徴は、クラフトとしてのクオリティーを求めていない点だという。「彼らは、いかにもプロが撮ったような動画はすぐに飛ばしてしまいます。明らかに広告コンテンツと分かるからです」。つまりUGCは広告としての機能性から判断すべき、という。
そこで重要になるのはブリーフ。通常のキャンペーンと同様、メッセージとして伝えたいことが絞られているか否かが鍵となる。「伝えたいことが5つも6つもあると、15秒のテレビCMならばただカタログを読み上げるような表現になってしまう。効果的なコンテンツを具現化するには、主題を一つに絞ることです。UGCも同じ。ブリーフがしっかりしていれば、インフルエンサーないしクリエイターがファンに向けて自分なりのメッセージングをしてくれます」。
広告主が更に気を付けねばならないのは、「制約と余白」だ。例えばUGCを信用していない広告主は、1から10まで決めごとを作ってしまい、結果的に全てのコンテンツが同じようなものになってしまう。肝要なのは、ある程度のルールを設定する「制約」と、各人がオリジナリティーを発揮できるような「余白」を同時に与えること。一つの成功例として同氏が挙げるのが、TikTokがモード学園と協働した「#モードランウェイ」。自分なりのお洒落をして街の中でポーズを取るというルールだけを決めて作品を募集、その結果2万本余りの動画が集まり、再生回数は1億2千万回に達したという。
では、ターゲットオーディエンスとの効果的なコミュニケーションはどうすれば取れるのか。まず大切なのは、そのプラットフォームを使う人々、そして彼らが何を面白いと思うのかを理解すること。「アドテック(東京2019)で話題になったのが、『上司がTikTokをやるべきか否か』ということでした。40〜50代の人々は余り利用しませんから。でもやはり、見ているだけではダメなのです。自分で投稿し、どのようなフィードバックがあるかを体験して、初めて見えるものがあります」。
中高年層はよく、若者がSNSをやる理由は承認欲求、つまり「いいね」が欲しいからだと主張する。「僕は、実はそうではないと思うのです。彼らは純粋に楽しんでいるだけ。自分が面白いと思ったことを皆で共有できる喜びだと思っています」。中高年層も投稿してそのコミュニティーに加わることで、初めて若い世代の価値観が理解できる。つまり、「空気が読める」ようになるという。
「広告主にとって一番いけないのは、『広告費を払っているのだから、いつでもどこでも広告を出す権利がある』という発想。(コミュニティーの)皆が楽しんでいるところにいきなり割り込んでくるような、空気が読めない投稿は最も敬遠されます。今は広告が簡単にスキップされる時代。コミュニティーの雰囲気を捉え、的確なコミュニケーション手段を取ることが肝要です」
加えて、身近にいるデジタルネイティブ世代と直に触れ合うことも大切だ。「95年生まれであれば、もう新人社員として会社にいる若者たちです。だから彼らと話をしてみる。それもお酒やゴルフを付き合わせるのでなく、ランチを一緒にすればいいでしょう。ランチならば彼らにとっても敷居が低く、気軽に参加しやすいと思います」。
では、UGCを含めた今後のマーケティングのあり方はどうだろう。現在普及しつつあるオムニチャネルマーケティングは、どのような影響があるのだろうか。「業界では360から365へ、とよく言いますが、いろいろなメディアで情報を発信する360度のマーケティングから、365日消費者に寄り添うマーケティングへと変化しつつあることは確か。これはオムニチャネルの考え方に近いですね。ファネルの概念が崩れ、サービスやコミュニケーション、消費などが一体化していく。ゆえにこれからは、実際の店舗も含めてすべてのタッチポイントを統合的にオーガナイズできる人材が求められるようになるでしょう」。
(文:水野龍哉)